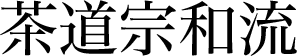金森宗和は、飛騨高山藩二代藩主金森可重の嫡男として天正十二(一五八四)年、 飛騨高山城に生まれ、重近(しげちか)と言いました。金森家の三代を継ぐべき立場でしたが、 慶長十九(一六一四)年、大坂冬の陣の出陣当日に父・可重より勘当されています。 理由については諸説があり定かではありません。
廃嫡された宗和は、実母である室町殿とともに京都に移り、当初は宇治の茶師・宮林源造の もとに滞在したと言われています。その地所には宗和自作の門が残っており、同家が製造した 茶のうち、「祝の城」「明石」は宗和の銘と伝わっています。 さらに、宗和が宇治滞在中に茶の木の古株を刻んで人形をつくったのが茶の木人形の始めという 伝承が残されています。 同年、大徳寺第百五十代傳叟紹印和尚に参じて剃髪し、宗和の号を 贈られました。
宗和は茶道を千道安に学び、また、古田織部の影響を大きく受けたとも言われています。 京都に移ってからは、宗和の茶は特に宮中で信頼され、鳳林承章や安楽庵策傳、近衞應山、 常修院宮慈胤法親王、一条惠觀らと親交を結びました。
その後、慈胤法親王や後西天皇、豫樂院らによって公家の茶が確立されますが、そこには 宗和の茶が大きく影響を与えました。また、好みの茶道具を宮中や加賀前田家を始めとした 各藩に紹介し、殊に野々村仁清を指導したことでも知られます。
加賀藩三代藩主の前田利常は、不遇の日々を過ごす宗和を憐れみ、高禄を以て召し抱えようと しました。しかし宗和はこれを固辞し、代わりに当時十五歳であった宗和の長男・七之助を 出仕させました。こうして、宗和、七之助の仲介により、宗和流の茶道とともに宗和や仁清の 茶道具も加賀に伝わりました。以後四十年間、加賀における茶道は宗和流が主流でしたが、 加賀藩五代の前田綱紀が裏千家四代の仙叟宗室を招いたことで、裏千家と宗和流が共に伝わる ことゝなりました。
七之助が寛文四(一六六四)年、五十五歳で世を去ると、長男の平蔵方一(三代)が六歳に して家督を継ぎますが、方一も二十三歳の若さで他界してしまいます。その長男の内匠信近(四代) が三歳で跡目を継ぎ、若くして継承する家元が続きます。信近(四代)は四十九歳まで、その長男、 多門知近(五代)は六十六歳までと天寿を全うしますが、後継ぎがいなかったためか、奥村主税の 四男、猪之助成章(六代)が養子に迎えられて金森家の当主となります。成章が五十五歳で歿すると、 さらに奥村主税の五男、量之助知直(七代)が養子となって後を継ぎますが、文化四年六月に自害し、 金森家は一時断絶となってしまいます。そのため、奥村主税が宗和流茶道を一時預り、門人たちに よる協議の末、流儀では血縁に依らず、この道に通達し、学識人格兼備の人を選んで宗家を継承する こととしました。こうして多賀直昌(宗乗)が選出され、八代となりました。宗乗は、流儀を継承 するとすぐに隠居して『拾玉抄』等の秘伝書を編纂し、積極的な活動を行ったことから、流儀に おける中興の祖とされていますが、三十八歳で他界。高弟の九里歩正令(黙々)が九代、その長男の 止少庵一蓬が十代を継ぎました。
明治維新を迎えて茶道等の日本文化に不遇の時代となりますが、一蓬の歿後、新宮教 のもとで 神事に奉仕していた高弟の安達弘通(司少庵宗香)が十一代を継ぎ、社会文化復古に尽力しました。 宗香が亡くなると、辰川宗弘(此松庵)が宗香所持の茶室を自邸に移築して十二代を継ぎます。 次いで、辰村宗興(吟風庵)が十三代となり、『茶道宗和流』を編集し、『拾玉抄』を上梓して 一般に配布するなど流儀に貢献しました。宗興歿後、その妻であった、辰村宗榮(椎陰軒)が十四代を 継承します。宗榮は能登出身の畠山即翁による勧めで東京に移り、殊に東京方面での流儀の発展に尽力。 宗榮が世を去ると、長男の辰村宗恍が十五代を継ぐものの家業が多忙であったため、東京宗和会会長の 堀宗友(青々庵)が補佐を務め、宗恍の歿後は宗友が十六代を継ぐこととなりました。 平成十四年十一月に宗友が歿すると、増田宗蒔(瑞枝庵)が十七代となり、平成二十七年一月、 宗蒔が代を譲って、宇田川宗光が十八代を継ぎ、現代に至ります。